こちらは、2023年12月23日〜2024年1月13日に行ったイギリス取材のレポートです。
<目次>
・カレーへ
・「街の中心部、駅から歩いて5分ほどの橋の下」
・シリア人はみな家族
・空き地での炊き出しへ
・「不法移民」の多様な背景
前回は、ドーバー海峡を渡って「不法移民」がやってくるイギリス南東部のドーバーを、2022年にイギリスに入国した兄アブドュルメナムと甥エブラヒムと訪ねたエピソードについて書きました。また彼らが、トルコでどのような境遇に悩み、どのようにイギリスを目指したのかについて触れました。今回は、イギリスを目指す「不法移民」が、ドーバー海峡を渡るための拠点、フランス北部のカレーを訪ねたエピソードです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
イギリスを目指す移民の船出の拠点、カレーへ
「ドーバーの街の灯りを近くに見たとき、船に同乗していたみなが涙し、歓声をあげた。ただただ、安心した」。2022年11月、ドーバー海峡を渡り、イギリスに上陸した日のことを、夫の兄アブドュルメナムはそう回想していました。
フランスのカレーの海岸からは、夜になるとドーバーの街の灯りが見えるそうです。不法入国を斡旋する業者は、海を渡るタイミングを見計らって移民たちに船を用意し、集まる場所と時間を指示します。しかし、彼らはその船に同乗することはありません。
「見ろ、あれがドーバーだ。あそこに向かって漕ぎ続けろ」。移民たちは業者にそう指示され、小型ボートに乗り込みます。そして、海の向こう、うっすらと街の灯りが見える方角へと、一心に漕ぎ出していきます。うまくいけば、ドーバーまでは4〜5時間の距離です。もし、海が荒れなければ。強風が吹かなければ。
アブドュルメナムたちが、どのように海を渡ってきたのかを知った私は、彼らの旅の足跡を追うため、フランスのカレーに向かうことにしました。本当は、海底トンネルを走っている電車でフランスに向かった方が、料金もずっと安いのですが、やはりドーバー海峡を渡る移民の取材なのだから、自分も船で海を渡らなければ、と思いました。イギリスのドーバーからはカレーまで、フェリーが一日数本出ており、ちょっと割高でしたが、こちらでカレーに向かうことにしました。

カレーまでは、フェリーで所要時間わずか90分。料金は、子供二人分を合わせ、三人で70ポンド(約14000円)です。船の内部にはカフェやバー、ゲームコーナーまであり、広いロビーには上質のソファーが並べられていました。ちょっとした豪華客船なのです。


15時半に出港してまもなく日が暮れ、あたりは真っ暗に。船の後ろに見えるドーバーの街の灯りが、飴玉のように赤や白や黄色に光り、遠ざかっていきました。この灯りこそ、移民たちにとりイギリス本土の目印なのです。
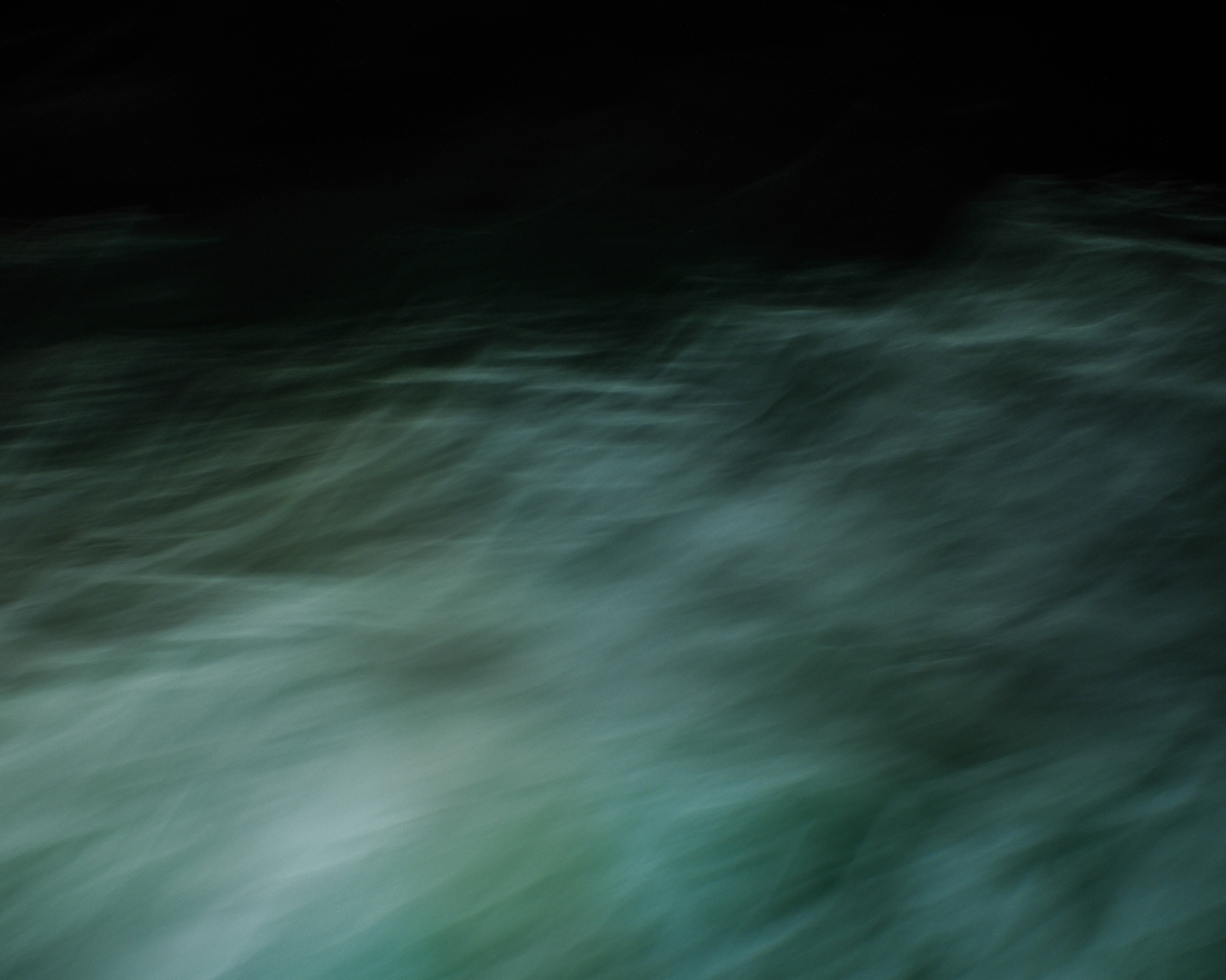


ほどなくして今度は進行方向に、チラチラと街の灯りが見え始めました。フランスの港町、カレー。海を渡る移民が、船出を待つ拠点とする街です。

入国審査を済ませ、カレーの中心部に移動する途中、30歳ほどのイギリス人男性と同じタクシーに乗りました。ロンドンで金融業のコンサルタントをしているという彼は、移民の衣食住をサポートするNGOでのボランティア活動を5年前からカレーでしているそうで、今年も6日間の活動のため来たそうです。移民への厳しい対処を打ち出しているイギリス人でありながら、移民のためのボランティア活動を休日に行っているという彼に、私は質問をしました。
「イギリス政府は今、不法移民に対して厳しい政策に転じようとしていますよね。実際に、移民の現状に触れながらボランティアされているあなたは、その動きをどう考えていますか」
「イギリス政府はクレイジーだ。移民にも、望む人生を選択ができる正当性があるはず」、彼の答えは驚くものでした。彼によれば、確かにイギリスでは、不法移民のこれ以上の受け入れに不満を持つ国民も多い。だが一方で、自分のように、受け入れを進めることで、将来的なイギリスの「人的資産」に繋げられるはずだと考えている若い世代も少なくない、とのことでした。見るからにスマートで、知的な雰囲気を漂わせるこうしたイギリスの若者の「人的資産」という観点からの意見に、なるほどと思うのでした。また、「移民にも、望む人生を選択ができる正当性があるはずだ」という言葉が胸に残りました。
「街の中心部、駅から歩いて5分ほどの橋の下」
その夜、ホテルに着いた私は、子供にご飯を食べさせて寝せて、それからようやく一息をつきました。移民の取材に入るための準備よりも、まずは取材に同行している子供のお世話をしなければなりません。小さな子供を連れながらの取材は、費用面でも体力面でも、そして精神面でも楽ではありませんが、自分がやりたい取材をやっている、という実感があるので苦にはなりません。
ようやく子供たちを寝かしつけた私は、アブドュルメナムに電話をし、カレーに到着したことを伝えました。実はカレーでは、ある目的がありました。海を渡る直前、アブドュルメナムたちが滞在し、野宿していたその場所を、この街で探すというものでした。それにより、不法移民という存在についてより理解を深めたかったのです。
その場所について、アブドュルメナムはこう説明しました。「街の中心部、駅から歩いて5分ほどの橋の下」だと。彼らがこの街にいたのは一年前の2022年の10月のことで、すでに気温は低く寒い日々でした。毎日焚き火をし、小さなテントに眠ったり、毛布をかぶって1ヶ月ほど野宿をしたそうです。橋の下を選んだのは雨が避けられ、わずかでも強風も避けられたからだそうです。同時に、駅に近い場所であることも重要でした。イギリスへの船は、カレーから少し離れた近隣の街の海岸から夜間に出ます。そのため駅から近い場所で待機していなければ、急な船出の連絡があっても電車移動ができないのだそうです。
翌朝、ホテルの窓のカーテンを開けると、カレーの空はどんよりと重い雲が立ち込めていました。雨が降りそうです。街には中世に建築されたキリスト教建築と思しき美しい塔がいくつも伸びており、晴れていたならどんなに美しい景観だったろうかと思いました。その眺めは、海からの入り口として栄えたこの街の歴史を彷彿とさせました。


その日、ホテルを出た私は、観光案内所でもらった街の地図を広げ、アブドュルメナムから聞いた橋を探しました。「街の中心部、駅から歩いて5分ほどの橋の下」。そう広くないこの街で、その場所はきっと見つかるだろうという確信がありました。
移民たちがたむろしているだろう場を探し、私は通行人にも声をかけました。
「ゴミが散乱しているところに彼らはいます(彼らがゴミを散乱させている、というニュアンス)」とちょっと嫌味を含ませて答える若いフランス人男性や、「彼らはよくこの辺りをうろついている。ひと目見れば服装でわかる」と答えたお年寄りがいました。
通行人のそうした口調からは、この街に大量に流入し、長く逗留するようになった移民たちに対し、あまり良い印象を持っていないことが感じられました。
シリア人はみな家族
カレーの駅のロータリーのすぐ近くに、土色に濁った小さな川が流れていました。その川にかかる橋の下に視点を落とした私は、「おや!」とあるものに目が釘付けになりました。そこには、着膨れした15人ほどの男性たちが焚き火を囲んで集まっているではありませんか!!その独特の雰囲気は、遠目にも彼らが、移動中の移民たちであることを物語っていました。こうして私は、アブドュルメナムから聞いたその場所を、実際、あっけなく見つけたのでした。


私は橋の下の移民たちに接触すべく、二人の子供たちの手を引き、ぐんぐんとそこへ近づきました。ヨーロッパを移動していく移民を実際に目にするのは初めてのことで、正直に言えば、私は興奮しました。歴史の動向を、すぐ目の前にしているのだという思いがあったからです。

私が近づくにつれ、彼らは警戒した視線でこちらを見ていました。「シリア人ですか?」と私が話しかけると、一人の男性がこわばった表情のまま「そうだ」と答えました。突然現れた子連れのアジア系の女性に、彼らはかなり警戒したようでしたが、私は、夫がシリアのパルミラ出身で、夫の兄も彼ら同様、ここから一年前にイギリスに渡り、難民収容施設に入っていること。この場所はその兄から教えてもらったことを話しました。そして事前にアブドュルメナムからもらっていたカレーでの一枚の写真―――まさにこの場所で焚き火の前で座っている―――をスマホで見せたところ、「本当にここだ!」と彼らは喜びました。私はアブドュルメナムとビデオ通話をし、この場所を見てもらい、さらに彼らと話してもらいました。


アブドュルメナムは確かに一年前、この場所に寝泊まりし、船出を待っていたそうです。そしてここは、移民たちが次々とイギリスに渡って行っても、後から来たシリアからの移民によって引き継がれていたのでした。
「ああ、自分もここにいた、懐かしい」と話した電話口のアブドュルメナムは、そこにいたシリア人たちを励ましました。さらに、イギリス政府の政策が厳格化に向かっているので、今からでもドイツのほうが行き先としていいかもしれないと、疲労感を交えた表情で、率直な胸の内を話していました。しかしそれを聞くシリア人たちは、「いいや、ここまで来たんだから自分たちはイギリスに行くしかないよ」「イギリスが一番いいはずだ」と笑顔で返していました。
その会話はまさに、一年前のアブドュルメナムに、現在のアブドュルメナムが語りかけているようでもありました。カレーのシリア人たちは、決して疑っていなかったのです。ただイギリスに行きさえすれば、生まれた国の国籍から生じる、この複雑な問題は全て消え去り、自分の人生は好転していくばかりだと。彼らは密入国の斡旋業者からの船出の指示を、ほぼ一カ月近くにわたって今か今かと待ち続けていました。
アブドュルメナムとの通話後、シリア人たちの私たちへの怪訝な眼差しは一転し、「ナフヌ スーリーン クッロ アーイラ」と誰ともなく言い始めました。アラビア語で「シリア人はみな家族」という意味です。アブドュルメナムが、「彼女は弟の妻でシリア人の家族だから、親切にしてあげて」と頼んでくれたようで、彼らは私を「オフティ(アラビア語で“私のお姉さん”、つまり砕けた意味で“同胞”の女性名詞)」と呼び始め、また私の二人の子供たち、サーメルとサラームが、流暢なアラビア語を話すことに喜び、子供を抱っこしたり手を繋ぎ、大変に可愛がってくれました。大家族が多いシリア人たちは、みんな子供好きで、その扱いにも長けているのでした。
橋の下を拠点としているらしいこのシリア人たちは、16歳から35歳ほどの男性で、ほとんどがシリア南部のダラー出身でした。大体がシリアから飛行機でリビアに移動し、そこから地中海を密航。イタリアに上陸後、隣国フランスまで歩いてきたとのこと。シリアからは2カ月ほどの道のりで、なかには密航が露見して、リビアの刑務所に半年近く入れられ、ここまで1年以上かかったという人もいました。リビアの刑務所で、看守に殴られたり蹴られたりの暴行を受けたという若者もおり、顔や腕などに、その傷跡が生々しく残っているのも見せてもらいました。
シリアのなかでも、特に南部ダラーからの移民が激増しているらしく、その背景には、ダラーでは政府への協力が強要され、若い男性は徴兵に加わるか、国を出るかの二者択一が迫られている現実があるようです。またシリアでは、この10年で物価が約20倍に高騰するという経済破綻に加え、インフラもほぼ崩壊し、仕事もなく、この国でこれ以上この生活を続けることに未来を考えられない、という背景があるようでした。印象的だったのは、彼らのほぼ全員が結婚しておらず、「金がなく結婚もできない」とぼやいていたことです。仕事もなく、妻や生まれてくる子供の生活を保証する資金も作れない。そうした境遇も、故郷を離れた一因のようでした。
空き地での炊き出しへ
ドーバー海峡を渡ろうとする、こうした移民たちの生活のサポートをしているのが、イギリスとフランスのNGOです。毎日、朝と夕方に食事の炊き出しが行われる他、三日に一度ほど、シャワーを浴び、スマートフォンの充電をし、洗濯物も洗って乾燥させられる施設を利用することができるとのこと。ここフランスの土地にいるならば、同じ人間として彼らが決して飢えることなく、人間として最低限の生存環境が保障されるように人道的な配慮がなされていました。


昼頃、彼らに誘われて炊き出しに向かうことになりました。その会場は郊外の空き地らしく、彼らとバスに乗って移動しました。フランスでは公共政策でバス代がなんと無料です。車内はあちこちから集まってきた30人ほどのシリア人に占拠され、異様な光景に見えましたが、乗り込んでくるフランス人と思しき乗客たちは、別段驚くこともなく、この光景が日常のものであるようでした。


20分ほど経ってバスを降りると、小雨が降っていましたが、やがてそれは激しい雨に変わりました。濡れながら、誰も傘などささず、私たちは道路脇を長い列になって進んでいきました。長男サーメルはエイハムという男性に手を繋いでもらい、次男サラームは複数の男性たちに抱っこや肩車され、頭が濡れないよう毛糸の帽子まで被せてもらっていました。
その途中、食事を終えて戻っていく移民とすれ違うたび、シリア人たちは親しげに挨拶を交わし、私にその出身地を教えてくれるのでした。今カレーで特に多いのはスーダン人で、アフガニスタン人、エジプト人もいる。シリア人はこの街に今、200人ほどいると聞きました。



やがて、トラックの脇に長い列ができた炊き出し会場に到着しました。大鍋から紙皿に盛り付けられるのは、鶏肉とニンジン、ジャガイモ、豆などを煮て、ご飯にかけたもの。雨晒しのなか、食事は雨水でびしょびしょになりましたが、シリア人たちは気にすることなく、談笑しながら平らげていました。

















その後、全身をひどく濡らしながら、私たちはあの橋の下に帰りました。全身が雨で濡れてしまい、「寒い」と震える子供たちのため、シリア人たちが火を焚いてくれました。燃料の薪もNGOから配布されるそうですが、それだけでは足りないため、古い靴や、衣類、木片など、燃えるものをなんでも拾い集めて燃やし、燃料にするのだそう。焚き火の煙が目にしみ、私たちの服は、あの独特の燻された匂いが奥深くまで染み込みました。焚き火を囲み、濡れたジャケットやズボンを黙って乾かすその輪に一緒に座りながら、ここがフランスの、しかも街中であることが信じ難い思いなのでした。




「不法移民」の多様な背景
焚き火に集まるシリア人移民たちは、みなこの辺りの路上で寝泊まりしているかと思いきや、なんとホテル暮らしのシリア人移民もいました。聞けば、80ユーロ(約¥14000)の部屋に六人で寝泊まりし、宿泊代を分割しているとのこと。橋の下で寝泊まりしているシリア人と何が違うのか、とストレートに尋ねると、「金があるかないかだ」という答えが返ってきました。いくら6人で宿泊代を割っているとはいえ、一カ月もホテル住まいというのは、大きな出費です(一人当たり負担額が1日約2500円、1ヶ月では約75000円)。しかも彼らは、この街に来るまで、すでに約10000ドル(約¥150万円ほど)をかけてきたらしいのです。こうしたホテル住まいのシリア人の多くは、首都ダマスカス出身者で、よくよく見れば、着ている服や靴、髭や頭髪の手入れも野宿組とは雰囲気が異なり、育ちの良さや裕福さが滲み出ていました。ここで知ったのは、「不法移民」として国境を越えようとする人々は、必ずしも貧困が背景にあるとは限らないことです。ただ国籍の問題によって、正規の手段で国境間の移動ができず、「不法」手段をとらざるをえないのです。

「不法移民」と一口に言っても、共通しているのは「不法に国境を越えていく」という点だけで、その背景は実に多様です。さらにヨーロッパまでのこの移動自体が、高額な資金が必要とされることを考えると、彼らは完全に頼る者のない貧困層とは言えず、むしろ財産を拠出できる「つてのある人々」でもあります。最近では、移民たちが経済的安定を求めて移動してきた「経済難民」なのか、もしくは紛争国での迫害から、真に人道的保護が必要な「難民」なのかを厳格に再定義する動きもヨーロッパの国々では生まれているようです。人道的寛容さから移民を今後も受け入れ続けるべきか、それとも法を厳格化し流入を管理するべきか。ヨーロッパの移民受け入れ国では、その論争が今日も続いているのです。




その日、降り続ける雨の中を、子供たちの手を引いてホテルに帰りました。ホテルでは、暖かいシャワーを浴びたいと思いながら、橋の下で今も焚き火に当たっているシリア人たちに、申し訳ない思いでした。


ホテルまでの帰路、広場にはメリーゴーランドが回っており、着飾った人々が、ごく普通に、メリーゴーランドを楽しんでいました。つい先ほどまで焚き火にあたって過ごしていた移民たちの世界と、この街の住民の日常の世界。肌で感じたその大きな乖離に、私は呆然としてしまうのでした。

明日も早朝から、シリア人移民たちの様子を見せてもらう約束をし、ホテルへと帰りました。
<引き続き、次回も、シリア人移民たちと過ごしたエピソードをご紹介します>
